節子…それ、ドロップやない、オハジキや
https://ex14.5ch.net/test/read.cgi/news4vip/1146382349/
「知ってる」節子はそう呟くと、銃口を清太の胸へ向けた。その表情は、「この距離ならば外さない」そういっているように見えた。
「どうして」
「どうして?」下らない質問に苦笑する。元々自分の兄はあまり頭がよくないことは節子自身よく知っていたが、ここまで愚かだったとは。
「誰のせいでこうなったと思ってるんや」
「――それは」
「あんたのせいや」清太の言葉を遮って断言した。「あんた以外誰がおるん」
さっと清太の顔色が変わった。本当に愚かな兄だ。自分の妹だけは自分を頼ってくれていると信じきっていたのだろう。
「ちゃう」
搾り出すように、そして消え入りそうな声でそういった。それでさらに節子は苦笑してしまう。ああ、こんな人間が自分の兄だったとは。
「ちゃう? じゃあ誰や。おばさんとでもいうつもりか?」
「……そうや」
「待遇はよくなかったかもしれへん。でもよう面倒見てくれてた。それなのに勝手に出て行ったのは誰や?」
「お前も、賛成しとった」
「考えがあると思っとったわ」節子は言いながら自分も愚かだったことを悔やんだ。こんな人間を少しでも信じた暢気さを。
「あそこまで先を見とらんと知っとったら、ついていかへん」
「うそや」
「そうやって逃げるつもりか? まさかこの状況が悪い夢や思っとるのか?」
「……ちゃう」
清太の声は少しずつ、しかし確実に小さくなっていった。
「だとしたら、どうするんや。俺を殺すんか?」
「そうや」即座に答えた。「お前の肉でも食えば、少しは長生きできるやろ」
言いながら自分でも笑みが零れているのがわかった。ロクなことをしなかった兄を、血が繋がっていると考えるだけで怖気がした人間を、やっと殺すことが出来ると。
しばらく俯いて震えていた清太が、突然後ろを向き走り出した。しかし恐怖からか足元がもつれ、無様にも転げて言葉にならない声をあげている。
「本当に、どうしようもないな、お前は」そういうと、節子は清太の足を「オハジキ」――お笑いだ。ピストルで打ち抜いた。
いよいよ清太は死を間近に感じたらしく、悲鳴と自分へ向けた罵詈雑言をわめきちらした。ああ、やはりこの程度の人間だったのだ。こいつは。
「人がくるわ」民家から離れているとはいえ、このまま騒がれれば人が集まってくるだろう。「さっさと殺すか」
「ひっ」銃口を向けられた清太は少しでも遠くへ逃げようと、地面を引っかきはじめた。しかしそれが無駄な行為とわかったのか、こちらに向き直り、言った。
「助けて」
それは節子にとって、幾分マシな言葉に思えた。「今までの恩を忘れたのか」などと言い出そうものならば、額を撃ち抜く気でいたからだ。
「死にたくない」今度は、そういった。
「そうか」
「えっ」
「死にたくないか」
清太はきょとん、としたが、すぐに意味を理解したらしく、勢いよく頭を振った。
「ああ……ああ!」
「ほんなら、ここから消えろ」それは足を撃ち抜かれた人間には酷な命令かもしれなかった。しかし出来ないのならばここで殺すだけだ。
「目障りや」
清太は返事もせずに、這って集落の方へ向かっていた。その背中に――いや、身体に、といったほうが相応しいだろうか。釘を打っておいた。
「人呼んでも無駄やで」
振り返りもせずに進み続ける。
「死人が増えるだけや」
それだけいって節子も身を翻す。
二人とも、一度も振り返ることはなかった。
目覚めは爽快だった。もしかしたら今までで一番の目覚めだったかもしれない。
昨夜は、野良犬を獲ってその身を食べた。食物連鎖の最後は、自分だと誰にともなく宣言しながら。
あの愚か者はどうしただろうか。おばの家に転がり込んだだろうか。あのおばなら嫌な顔はしつつも、寝床だけなら与えてやるだろう。
「くだらん」
それは自分自身に向けた言葉だ。あんな下らない人間のその後など考える必要もない。
そう結論を出すと、節子は再度横になった。
結局、眠ることは出来なかった。
「くっ」
足に熱い鉄の棒を突き刺されたような痛みが走った。銃弾が体内に残らなかったことだけが、唯一の幸運だった。
おば――久子は玄関前で血を流しながら倒れる清太を見つけると、家族総出で大騒ぎをしながら止血をし、以前清太たちを泊めていた部屋に運んだ。
痛みと熱に喘ぎながら、清太は久子に謝った。「すんません、すんません」と、繰り返した。「黙っとき」と凄まれたので、すぐに黙ることにしたが。
「今日お医者さん、来るからな」襖を少しだけ開けて、久子がそういった。「おかゆ、食えるか?」
「すんません」
「言いっこなしや」
「すんません」
「おかゆ作るから、待っとき」
それきり、清太は瞼を下ろした。
突然何者かに猟銃で撃たれたと、そう説明した。食料が溢れてるわけでもないのによく肥えた医者は怪訝な顔をしたが、そう追求はせずに縫合をして、「歩けるようになるまで、大変だよ」といって帰っていた。
節子は栄養失調で死んだことにしておいた。今の節子のことをいっても信じるはずがなかったからだ。変わり果ててしまった節子のことを。
今思うと、節子は最初からああだったのではないだろうか、とも思う。あのドロップが大好きな節子は偽りだったのではないだろうかと。確認のしようがないからどうすることも出来ないが。
日本が降伏してからは世の中が二倍速で進んでいるようだった。明治維新の後もこんな感じで時間が流れていったんじゃないかと思った。
そんな中でも、清太の時間はそれほど早く進みはしなかった。歩けるようになるまでは、どうしようもなかったからだ。
いち、に、いち、に。
ゆっくりと歩を進める。ずきん、とかすかな痛みが走るがそれでも足は止めない。
いち、に、いち、に。
清太の足はかなり回復していた。走ることは出来ないにしろ、歩くことは出来るようになっていた。毎日、目標を決めてそこまで歩くリハビリを続けている。
今日のゴールは、あの場所だ。血を分けた妹と、決別をした場所。清太と節子が兄妹ではなくなった場所。
「着いた……」
久しぶりに来たその場所は、何も変わっては居なかった。変わっていたことといえば、既に誰も住んではいない、ということだ。
「節子」と呟いてみた。懐かしい響き。
視線の先に、見覚えのあるものが落ちていた。そう、それは清太には見覚えがあった。
「――ドロップ」
正確にはドロップの缶、だ。持ち上げるとジャラ、と何か硬いものが缶にぶつかる音がした。
「おはじきや」
何故この中におはじきが入っているのだろうか。考えながら一個取り出してみる。赤く透き通るおはじきが出てきた。
「よう似とる」なるほどそれはドロップと似ていないこともなかった。節子は空っぽの缶にこれを入れてドロップに見立てていたのだろうか。そして味のしないこれを口に含んだりしていたのだろうか。
ありえない――。そう思った。あの冷酷な節子がそんなことをするはずもない。今自分が想像したことは偽りの方の節子がすることだ。
清太は缶を大事そうにポケットに入れ、そして今来た道をいち、に、いち、に。と戻っていった。
久子は、清太の尻と椅子がくっついているのではないかと時々本気で心配になる。
足もすっかり良くなり、皆で回復を祝っていた場で「奨学金で大学に行って、警官になります」と宣言した日からこっち、清太が外出するするところを、学校に行くとき以外で見たことがない。
夕飯だと部屋に呼びに行くと、例外なく学校帰りに買ってくる問題集を解いているのだ。問題集を買う金は、久子が出していた。小遣いだといって渡しても、清太は「必ず返します」といって問題集を買ってくる。清太の部屋に漫画はなかった。
今日も久子は清太を夕飯に呼びに、部屋の前に居た。今日も清太はわき目もふらず勉強しているのだろう。ひとつため息をついて襖を開ける。
「清太さん、ご飯出来たで」
「はい」振り返りもせずにそう言った。鉛筆を持つ手は動かしたままだ。
5分もすれば来るだろう。久子は襖を閉めた。
何故あの子はあそこまで必死になっているのだろうか。確かに目指しているものはそう簡単ではないが、何が彼をそうさせるのだろう。
あのとても仲のよかった妹――節子ちゃん、だったろうか。あの子の死――栄養失調といっていた――を自分のせいだと思っているのではないだろうか。
それならば自分にも責任はあると、久子は思っていた。そして自分はその分まで清太を養う義務があると、そう思っていた。
卒業式というものは実に退屈だった。今は「最後の授業」とやらを教室で執り行っている。
節子は、この場に居るほぼ全員が同じ中学へ行くというのに感慨深く泣いている同級生たちを半ば呆れつつ一瞥した。どいつもこいつも自分と同い年だとは信じられないくらいに頭が悪い。
頭が悪い、といえば教壇に立って「未来」とか「希望」とかありがちな単語を頻繁に使っている担任の男も同じだった。恐らくこの男は学園ドラマの主人公の気分でいるのだろう。身振り手振りで熱心になにやら語っている。
「夢を持ってください。大きな夢を。その夢は必ず――」少しばかり耳を傾けてみたが、嘲笑してしまいそうになる内容だったので、すぐにやめた。
小学校から中学校に上がって変わることとを節子は考えてみた。
あの男がそろそろ手を出してきてもおかしくないな、とどこか他人事のように、そう思った。
拍子抜けするほどにそれは達成した。
いつだったか、まだ非常に幼い頃。一目で「その道」だとわかる男の腕を、すれ違いざまに撃ったのだ。撃たれた男は何が起こったかわからなかったらしく、「なんじゃこりゃあ」と間抜けな悲鳴をあげ、隣を歩いていたいたチンピラの頭を叩きまくっていた。
節子は今度はわかりやすいように、その男の眼前に銃口を向けて、「あんたらの棲み家、どこや」といった。すると今度は突然笑い出した。
よくよく考えれば当然なことだと思えた。3,4歳の幼女が銃を持ち歩いて、その上それを人に向けているのだから。しかし節子はそれがとても不愉快で、今度は反対側の腕を、撃った。
チンピラは逃げ出し、その男は痛みを訴え、それから、「わかった」を連呼した。
「あたしのこと、飼わんか?」そう言われた脂ぎった男は、ぽかん、と口を開けていた。
そしてしばらくして「なんや」と隣に居た長身の男に「このお嬢ちゃんが、テツ撃ったって?」と訊いた。
長身の男が頷くと、脂ぎった男はひとしきり笑うと、「ええよ」といった。あまりにあっさりした返事だったので、これには節子も少しばかり動揺した。
それから数日して気づいたことがある。脂ぎった男――部下たちはそいつのことを「清田さん」と呼んでいて、苗字とはいえ節子にはあの愚かな兄が思い出されて不愉快だった――は、特殊な性癖を持っていることに。
「子供好き」といえば響きはいいが、その言葉の前に「性的に」をつければたちまちそれはおぞましい表現になる。とにかく、清田は、そんな性癖を持っていた。
しかし清田は手を出すことはなかった。どうやら見ていることだけというのが、清田の美学らしかった。小五の時、清田が自分の水着でそれを包んでマスをかいていたのを目撃したときは流石に貞操の危機かと思ったが。
小五でそれなのだから、中学にもなればそろそろ我慢出来なくなるだろうとは思っていた。清田に妻はいなかったし、いってみれば奴の最も近くに居る女は自分なのだ。
節子はそれを仕方のないこと、と覚悟を決めることにした。遅かれ早かれそのときはやって来ると思っていたからだ。
充実している。清太は自信満々にいうことができた。
警察官になって既に三年目になる。仕事は忙しいがやりがいがあるし、同棲中の恋人も居る。温子は自分の仕事にとても理解があって、優しかった。
今日も仕事でくたくたになりながら家路に着く。
「そういえば、もう少しで夏休みやな」
すっかり忘れていた。今年は三日間の連休が貰えたのだ。去年は結局どこにも行かなかったし――久しぶりに、おばさんとこに顔出すのもええかもしれん。温子の紹介も兼ねて。
我ながらいい案だ。そう思うと、清太はやや歩調を速めて、家に向かった。
久子は立派になって顔を出した清太を見ると顔が綻びっぱなしだった。おまけに、しっかりした恋人も連れて。
二宮金次郎の亡霊でも乗り移ったのではないかと思った頃を思い出すと、あれはあれでよかったのかも知れない。あれがなければ今の清太はなかっただろう。
「なんもないけど、ゆっくりしていきなはれ」
「言われんでも」という声を背中越しに聴くと、久子は台所へ向かった。昼ごはんは何がいいだろうか。買い物をしてきたほうがいいかもしれない。そうだ、まずは買い物だ。
「おばさま、何かお手伝い、しましょうか」
温子が言うが、久子は「かめへん、かめへん」といって急ぎ足で玄関を出て行った。
「忙しない人やろ」
清太がいうと、温子は「元気な人じゃない」と笑った。
やけに気合の入った久子と温子の共同作業の結晶の昼食を食べると、特にすることもないので寝転んだ。温子の「家にいるときと同じ」という呆れたような言葉は聞き流しておく。
「そうや」
唐突に、思い出したことがあった。
「そうや、そうやった」
さて、どうするか――。
節子は夏なのに震える体を抱きしめながら歩く。
人を殺したのは久しぶりだった。
11歳の幼女が自分の命を狙っているとは思いもしなかっただろう。自転車で通りすがりに、撃った。誰かは知らされていない。殺せ、と清田にいわれれば従うしかなかった。
それ以来だ。5年ぶりぐらいだろうか。今回は相手が誰かはとてもはっきりしていた。
自分を抱く清田が、何故だか突然醜い豚に見えたのだ。だから、衝動的に、撃った。銃声に気づいて入ってきた男たちも皆、撃った。
それから身体を洗って、長いこと寝床にしてきた場所に別れを告げた。
さて、どうするか――。
なんとなく、「ふるさと」というところに行きたい気分だった。お盆が近いせいかもしれない。
「蛍?」思ったより温子は食いつきがよかった。
「私、見たことない」
「ようさん集まるとこがあるんや」
久子が麦茶を持ってちゃぶ台に置く。
「ええ機会やし、いってみなはれ」
「綺麗やぞ」
「行く」はしゃぎながら立ち上がった。「行きたい」
「秘密の場所や」
「綺麗」ほう、と息を吐く。「本当に綺麗」
まだそれほど暗いわけではなかったが、それでも蛍は大量に飛んで、幻想的な光を放っていた。
「命を削っとるから綺麗なんやろな」
「どういうこと?」
「蛍はすぐ死んでしまうんや」清太の肩に蛍が止まった。「自分の命を削って光って、一週間もすれば死んでしまう。そういう生き物なんや」
「なんだか、かわいそう」
「かわいそうなもんか」即座に否定すると続けた。「精一杯生きとる奴のこと、かわいそうなんていったらあかん」
「立派なこと、よういうようになったなあ」
ぱん、と乾いた音がした。清太には、聞き覚えのある音だった。忌まわしい思い出として記憶の奥底に封印していた音だった。
「節子」
そして、忘れていた、忘れようとしていた名前を口にした。
「元気そうやないの」
それには答えず、すっかり大きくなった、と清太は場違いな感慨を覚えていた。あの時が――そう、4歳だった。もう16歳になるのだ。
綺麗になった、とも思った。大きい目に透き通るような肌で、漆黒の闇に溶けてしまいそうな髪。
「大きくなったな」
「おかげさまで、な」
心にもないことを、と清太は思った。温子に目をやると、怯えながら節子と清太を交互に見ている。
「紹介しとくわ」銃に警戒しながら、温子に近づく。「俺の大切なひとや」
「その愚か者の妹です」節子はにこり、と笑いながら銃口を向けた。
「温子を撃ったらお前でも許さんぞ」何故か心は落ち着いていた。今日があの日と同じ日だということに気づいてから、居るかもしれない、とどこかで思っていたのかもしれない。
「許さなかったら、どうするんや」
「殺す」
「殺す? あんたが私を? 出来るわけあらへん」節子は心底楽しそうに笑った。「無理や」
「無理やない」
かといって、何か考えがあるわけでもなかった。とにかく温子はこの場から逃げさせるべきだろうか。
「温子は関係あらへんやろ」
「好きにしたらええ。あんたはあかんけどな」
「そういうことや、逃げろ、温子」
「でも」「逃げろ」清太の迫力に、思わず駆け出していた。「おばさんにはいわんでええ。必ず戻る」
「誰のせいでそうなってしまったんやろな」そういうと節子は怪訝な表情を浮かべた。「誰や、いうたら、そうや、俺や」
そこまでいうと節子も理解したようで、表情に幾許か変化があった。
「4歳と14歳で生きようと思ったんや」
本心だった。あの頃の自分は、
「生きていけると思ったんや」
「ふざけるな!」節子が叫んだ。「私がどれだけ――」
「すまん」
「大変やったやろ」
「あんたに何がわかるんや!」
「わかるわ」じっと節子の目を見据えた。「わかるわ。兄貴じゃからな」
「すまん」もう一度いって頭を下げた。節子の表情は見えない。
「……もうええ」
銃を下げてそう呟いて、座り込んでいた。「もうええわ。疲れた。ここから消えろ」
これに背いたら撃たれるのだろうか、と思った。だが背くつもりもなかった。
「節子」
俯いた妹に、話しかける。返事はない。
「忘れもんや」
あの日から保管していた、ドロップの缶を節子の傍らに置いた。
「じゃあ――さよならや。節子」
これから自分はどうするのだろうか。清田たちを殺したことがばれて、追われる身になるのだろうか。それとも、ここで自ら命を絶つのだろうか。それとも、あてもなくさまようのだろうか。それとも、蛍のように精一杯生きようとするのだろうか。
わからなかった。
「どっちが阿呆かわからんわ」
自嘲気味にそういった後、節子は視界に広がる蛍を見つめていた。
精一杯に生きている蛍はとても綺麗だと、素直にそう思った。
夏だけあって、朝から日差しが強かった。
夜が明けて、清太はまたこの場所を訪れていた。
節子はどうやって生きていくだろうか――そう考えたが、すぐにやめた。考えたところでわかるはずもない。
ふと、目に入ったものがあった。ああ、これは。
「ドロップ――やない。おはじき、や」
清太は赤く透き通るそれを拾い一つ息を吐くと、今来た道を戻っていった。
なんとなく懐かしくなり、いち、に、いち、に。と呟きながら。
おわり。
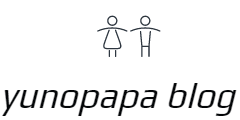




コメント